
監督・脚本:大友啓史
1966年、岩手県生まれ。1990年にNHKに入局し、連続テレビ小説「ちゅらさん」シリーズ(01~04)、「ハゲタカ」(07)、「白洲次郎」(09)、NHK大河ドラマ「龍馬伝」(10)などを演出。イタリア賞はじめ国内外の賞を多数受賞する。2009年、『ハゲタカ』で映画監督デビュー。2011年に独立し、『るろうに剣心』(12)、『プラチナデータ』(13)、『るろうに剣心 京都大火編/伝説の最期編』(14)、『秘密 THE TOP SECRET』『ミュージアム』(16)、『3月のライオン』2部作(17)、『億男』(18)、『影裏』(20)など話題作・ヒット作を次々と世に送り出す。『るろうに剣心 最終章 The Final/The Beginning』(21)では、2部作合わせて70億円、シリーズ累計200億円に迫る大ヒット。東映創立70周年記念作品の『レジェンド&バタフライ』(23)は、20億円を超える興行収入を記録。
+ INTERVIEW
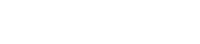
「いつか本土復帰前の沖縄を描きたいと思っていた」──大友啓史監督の長年の想いは、小説「宝島」との出会いで叶うことになる。以前、演出を担当した連続テレビ小説「ちゅらさん」の時代設定は1972年の沖縄本土復帰後、『宝島』は本土復帰前の20年を描いた物語だ。「本土復帰前の沖縄を描かないと、沖縄の人々の本当の気持ちは理解できないのではないか、そういう思いが強くありました。一夜限りの出来事として語り継がれているコザ暴動から露呈される、群衆のパワー、無軌道な感情の奔流、優しさの裏側に潜めた沖縄の人たちの、一線を越えた時の強さや激しさを映画で見せたい。米兵による交通事故を発端にした米軍支配の矛盾や不満の爆発をどうやって描くことができるだろうかと、腐心しながら取り組んだ作品です」。
企画の立ち上げから完成まで6年、コロナ禍によって撮影は二度、延期になった。踏み出すたびに引き戻される行き場のない怒りは、奇しくも『宝島』が内包する怒りとも重なった。そして、主演の妻夫木聡をはじめ、広瀬すず、窪田正孝、永山瑛太、これ以上ないキャスティングが実現。本土復帰前の20年間の沖縄を描くにあたり、俳優たちは、順撮りではないため設定年齢や感情を飛び越えながら日々の撮影に向きあう。「たとえば、クライマックスを撮影の中盤で撮らなくてはなりませんでした。そもそも、映画のなかでは嘉手納基地も舞台になっていますが、実際に我々が基地に入ることは、正当な手続きを重ねた取材ですら容易ではなく、俳優が自分の目で物語の舞台がどんな場所であるのか、その距離感や状況を事前に正確に把握することは難しい。そんななかで、ゲート通りから基地まではどのくらいの時間がかかるのか、そういったディテールを少しづつ現場で、我々のやれる精一杯の中で提示することで、妻夫木くんたちであれば、この物語に必要な熱量や匙加減を何らかの形で掴み取ってくれるはずだと、心配はしていませんでした」。
大友監督の演出の特徴は、こう演じてほしいという提案というよりはむしろ、俳優が台本から読みとり感じたものを、現場で受け取り、そこにフォーカスし、拡張しながら演出していく。シビれる瞬間はいくつもあった。そのひとつが、この映画のテーマに繋がるグスクとレイの芝居だ。台本にして約10ページ、時間にして約5分のシーンを振り返る。「かつて一緒に戦果アギヤーをやっていた親友に会って話しているうちに、自分の体の奥底に溜まっていたことが思わず出てしまうシーンですが、思っていることを言葉にする、意見を真っ正直にぶつけ合う、それって(今を生きる自分たちも)やっているようでやっていないんですよね」。二人の言葉が伝えるのは、個人的な感情だけはなく、沖縄の歴史や沖縄が背負ってきたこと、また今の世界で起きていることと地続きであるということだ。「この映画で描かれる時代は、ベトナム戦争が始まると世界中で戦争に対するデモが同時に起き、人間の共感力がポジティブに発揮された時代でした。今は、怒らない時代、優しい時代、共感を失いかけている時代。だからこそ、(グスクとレイのセリフは)それを巡る議論にもなっています。また、踏みとどまり続けて何か行動を起こしていくヤマコを中心にグスク、レイ、オンがいるような、実は彼女を中心に回っているとも言えるので、演じる広瀬さんには、色々な思いを込めて太陽でいてほしいと伝えました。そういう意味では、この映画は沖縄の物語であり、グスクたちの青春物語であり、アメリカ統治下のあの時代に、身をもって最前線に立ち続けた女たちの物語でもあると思っています」。
CLOSE ×
脚本:高田 亮
『そこのみにて光輝く』(14)でキネマ旬報ベスト・テン脚本賞、ヨコハマ映画祭脚本賞を受賞。主な作品に『きみはいい子』(15)、『オーバー・フェンス』(16)、『猫は抱くもの』(18)、『まともじゃないのは君も一緒』(21)、『ボクたちはみんな大人になれなかった』(21)、『死刑にいたる病』(22)など。
+ INTERVIEW
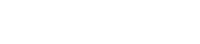
「大友監督で『宝島』を映画化するけれど、興味はありますか?とプロデューサーからお声がけいただいて。実は、過去に大友監督作品で脚本を作っていましたが、実現しなかったことがあったので、そういう経緯も含めてぜひやってみたかったですし、原作が持つ物語の厚み、戦果アギヤーの話や戦後の歴史を網羅しながら進んでいく青春物語、それをどう映画に繋いでいくのか、挑戦してみたい気持ちもありました」。
原作の熱量に惹かれ準備に臨むが、「東京出身の戦争を知らない世代の自分が、この話を書く資格があるのだろうか……」と葛藤もあった。資料を読み込み、実際に沖縄に足を運び、取材をすることで、どう向きあうべきかを探り続けた。「沖縄に行って、当時刑事だった方や学生運動をしていた人、Aサインのレストランをやっている人、いろんな人に会って話を聞くことで、複雑な想いを感じられました。たとえば、グスクとアーヴィンが協力して捜査する、お互いを利用しながら関係を深めていく、それは一体どういう感情なのかを描くにあたっては、沖縄で見聞きしたことがとても参考になっています」。
物語を引っぱっていくのはグスク。ヤマコ、レイ、オン、アーヴィンや小松、主要人物とそれぞれ対峙するのもグスクで、実はとても描くことの難しい主人公だった。「グスクはオンちゃんを探すために刑事になり、酷い事件に日々接しますが、もともとは飲んで歌って踊っていたい人です。でも、刑事になったことで沖縄の人々のために身を粉にして働くことになる。その葛藤が、グスクの魅力になっていると思います」。キャラクターの骨組みとして大切にしたのは何だったのか。「僕のなかでグスクの落とし所にしたのは、リアリストであることでした。その時のベストを選んでいくというか──戦果アギヤーで犯罪者だったのに刑事になって、オンちゃんを探すためなら、本来は敵であるはずのアメリカとも手を組む。でも、レイからすると何でお前はアメリカと……って許せない。だから対立する。物語のなかで、沖縄の歴史的な事件はとても重要な要素ではありますが、そこを掘り下げていくというよりも、様々な出来事に翻弄されながらも、オンちゃんを捜し求める3人の感情をパワフルに語る、それは脚本を書くうえで常に頭に置いていたことです」。グスク、ヤマコ、レイ、3人の感情のすれ違いをおろそかにせず語る、また全体の勢いを殺さずに物語を進めることも難しかったと言う。そして、要所要所でその存在感を際立たせるのが、永山瑛太の演じるオンだ。「沖縄の文化には自然信仰があったり、ユタと呼ばれる霊媒師のような方がいらっしゃったりするので、自然界や死後の世界が現実と溶け合っているような感覚で、主人公の三人が、行方不明のオンをいつもどこかに感じていると解釈していました。グスクが、ヤマコが、レイが、戦果アギヤーの頃のオンちゃんを感じる演技をするだけで、オンちゃんがそこにいるかのように見えてしまう。俳優の凄さを、そういうところでも感じました」。
CLOSE ×
企画・プロデューサー:五十嵐真志
主な作品は『ラッシュライフ』(09)、Netflixドラマ「火花」(16)、『彼らが本気で編むときは、』(17)。大友啓史監督作品は『影裏』(20)をプロデュース。
+ INTERVIEW
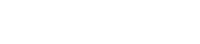
企画・プロデュースの五十嵐真志が、『影裏』に続く大友監督との企画を模索するなか出合ったのが、真藤順丈の小説「宝島」だった。圧倒的な熱量に強く惹かれたとふり返る。「大友監督作で好きなのは、「龍馬伝」や『ハゲタカ』といった熱い人間ドラマ。小説「宝島」にも同じものを感じました」。そして、出版元の講談社に連絡をとり、コンペの末、映像化の許諾をもらい、「二度と出合えない企画、生涯1本の企画と言っても大袈裟ではない」と、企画は本格的にスタートした。
映画として、どんな脚本にするのか、キャスティングや配給はどうするのか──「開発は一番楽しい時間でしたね。沖縄についての書籍や資料を読み、実際に沖縄に行きリサーチをするなかで、知識を詰め込むほどこの作品が背負う題材の大きさ、また沖縄が抱える問題の難しさをまざまざと感じ、大きなプレッシャーもありましたが、やっぱりこの原作を映画にできるというワクワク感が大きくて。背中を押される気持ちで前に進んでいきました」。
しかし、新型コロナウイルスの流行によって、映画制作は一旦立ち止まることになる。しかも二度。大きすぎる試練だ。「結果論としては、それでも諦めることはできなくて、乗り越えて作ってやろうと、逆に力が湧いたといいますか。立ち止まったことで、新たに応援してくれる人も増え、障害が大きくて多かったからこそ、たどり着けたと思っています。でも、やってみて分かったことですが、一度中断して立て直すことは、1が0に戻るのではなく、マイナスに落ちて、そこから0に戻してから再び1にする。ものすごく難しいことでした」。
そのなかで、五十嵐の心の支えとなったのは、企画の実現に向けて共に力を尽くしてくれた人たちと、とりわけ主演の妻夫木聡の存在だった。「二度の延期、普通ならスケジュールを含めて断られても当然であるのに、妻夫木さんは一緒に企画を背負ってくれて、信じてくれて、待つと言ってくれた。そうまでしても、やるべき価値があると伝えてくれたのが本当に嬉しくて、心強かったですね」。
そして2024年2月25日に沖縄でクランクインを迎えたが、試練はまだあった。この映画のヤマ場であるコザ暴動の撮影をオープンセットからスタジオのセットに切り替えたこと。クランクイン3週間前の決断だ。「それまで準備をしていたものが一からやり直しにはなりましたが、製作費を理由に制作を止めないためには、そうするしかなかったと思っています。これも結果論ですが、スタジオにしたことで、天候の心配はなくなり、夜のシーンも昼間に撮れる。ブルーバックでの撮影なので技術的な課題は新たに増えましたが、それをあわせても、この企画自体が持ち合わせている強運と生命力を感じています」。
映画『宝島』は、6年の歳月、25億円のプロジェクト費をかけた大作となった。「改めて思うのは、本屋で手に取り、読んだときに感じたあの熱量を、小説から映画に受け渡すことができたんじゃないかなと。映画の著作権は70年。プロデューサーは、ゆりかごから墓場までと言いますから、しっかりと見届けたいと思います」。
CLOSE ×
プロデューサー:野村敏哉
主なプロデュース作品は『集団左遷』(94)、『ホタル』(01)、『T.R.Y.』(03)、『海猫』(04)、『明日の記憶』(06)、『最後の忠臣蔵』(10)、『アゲイン 28年目の甲子園』(15)、『ヘルドッグス』(22)。
プロデューサー:角田朝雄
主な作品は『北の零年』(05)、『劔岳点の記』(09)、『Mr.マックスマン』シリーズ(15/17)、『鉄道員(ぽっぽや)』(20)、『きまじめ楽隊のぼんやり戦争』(21)、『少年と戦車』(22)。
プロデューサー:福島聡司
主な作品は『グーグーだって猫である』(08)、『ノルウェイの森』(10)、『謝罪の王様』(13)、『予告犯』(15)、『真田十勇士』(16)、『パラレルワールド・ラブストーリー』(19)、『首』(23)。大友監督作は『秘密 THE TOP SECRET』(16)、『るろうに剣心』シリーズ(14/21)、『レジェンド&バタフライ』(23)がある。
音楽:佐藤直紀
『永遠の0』(13)、『ゴジラ-1.0』(23)などで5度の日本アカデミー賞優秀音楽賞、『ALWAYS 三丁目の夕日』(05)で最優秀音楽賞を受賞。大友監督作はNHKドラマ「ハゲタカ」(07)、NHK大河ドラマ「龍馬伝」(10)、『億男』(18)『るろうに剣心』シリーズ(12/14/21)、『レジェンド&バタフライ』(23)など。
+ INTERVIEW
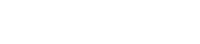
『宝島』は、映像も音楽も、青い海、青い空というリゾート的ではない沖縄を描いている。『ハゲタカ』にはじまり、数多くの大友作品の音楽をつくり出してきた佐藤直紀が、今回も音楽を担当する。「台本を読んで感じたのは、平和とは何か、生きるとは何かを見直す映画でもあるということでした。音楽にもその意味を込めたい──音楽の演出として、単に映画を引き立て見栄えを良くするためではなく、この台本(映画)そのものを内側から支える存在でありたい、そんな思いで取り組みました」。耳あたりの良さを追求するのではなく、目には映らない感情や空気の揺らぎを炙り出すような音楽を目指した。
高揚感ある既成曲のアメリカンポップスとのバランスも考慮し、佐藤は、この映画のために約30曲を作った。工夫のひとつとして、たとえば小学校に飛行機が墜落するシーン、最後にグスクとオンが向きあうシーンなどで流れる原始的な曲がある。「まず、提案したのは、男性の叫び声にも聞こえる歌(曲)です。福岡ユタカさんというアーティストの方に歌ってもらい、グスクらがどうやって困難を乗り越えていこうとするのか、怒りや悔しさ、悲しみ、心の叫びを代用できるような音として、福岡さんの声を使いました」。
大友監督からは、ギターアンサンブルの曲が欲しいというリクエストがあり、それにもユニークなアイデアで応えた。「ただのギターではなく、土着的な未完成の荒々しさのあるギターが欲しいということで、本来はギターで演奏するフレーズをウードという楽器を使って弾いてもらいました。ウードは琵琶のルーツでもある中東のフレットのない楽器です。ここを押したらこの音が出るというのではなく、指の加減で微妙に音程がずれる、やや不安定な楽器ですが、音程が曖昧になるところを、人間らしさ、不完全な感じとして表現しています。また、もう一つ特徴的な楽器としてカヴァルという中央アジアの楽器を使用しています。尺八より少し高い音色で、暗いフレーズが出せる。そのカヴァルでは、独自の音階を用いることで、この映画が求める“沖縄らしさ”を音楽面から表現しています」。
太陽が海に沈んでいくラストシーンで流れる曲は、エイサー(沖縄本島で盆時期に踊られる伝統芸能)に欠かせない三線や太鼓、指笛などを用いた。「ラストシーンからエンドロールにかけて、沖縄の伝統的な響きを強く打ち出すことで、作品の根底にある思いと音楽を再び交差させることを意図しました」。
音楽が担うのは、感情の喚起や増幅、その作品の世界観など多岐に渡るが、当然のことながら、どう寄り添うかは作品ごとに異なる。佐藤が『宝島』で心掛けていたのは抑制だった。「饒舌になりすぎないことで、音楽的にはやや控えめに感じられる部分もあるかもしれませんが、今回の『宝島』はエンターテインメントとしての側面に加え、戦後沖縄を舞台に、史実を踏まえながらも、これまで語られてこなかった物語や視点が描かれています。決して謳いすぎず、だからこそ静かに響く余韻や言葉にならない感情が残るように意識し、作品のテーマと真摯に向き合いながら音を紡ぎました」。
CLOSE ×
撮影:相馬大輔
『ゴールデンカムイ』(24)で第48回日本アカデミー賞優秀撮影賞を受賞。主な作品は『SP』シリーズ(10/11)、『ヘルタースケルター』(12)、『TOKYO TRIBE』(14)、『セーラー服と機関銃 -卒業-』(16)、『人魚の眠る家』(18)、『いのちの停車場』(21)、『52ヘルツのクジラたち』(24)ほか多数。
+ INTERVIEW
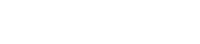
1952年から20年間の沖縄を描くにあたり、撮影の相馬大輔は、ロケハンでの肌感も参考にしながら、年代やシチュエーションのトーンを決めることから取り組んだ。「まず撮影部としては、沖縄の風土を考慮して、昼のシーンは太陽の光を感じるような設定、夜のシーンは月明かりのような自然の光、コザ暴動を目立たせるために街の明るさは抑える。そんな感じで、最初は7つか8つのトーンを用意するつもりでしたが、クランクインの時には38パターンくらいに膨らんでいました」。それだけ熱の入る作品だという証でもある。
大友監督作品は今回が初参加となる。大友監督にトーンについて説明する際、参考例として挙げたのは、『シティ・オブ・ゴッド』『マッドマックス』『デリカテッセン』、そしてウォン・カーウァイ監督の初期のタイトルなどだった。大友監督の過去作を研究しつつ、初めてタッグを組むからこそ「この『宝島』で、今までにはない“大友ルック”を生みだせたら──」という提案もしたと言う。「大友さんの映画の特徴のひとつは、登場人物たちの怒りや衝動をダイレクトに伝えていること、そこが魅力のひとつです。今回は、沖縄の人たちの鬱屈した気持ち、アメリカ統治下のストレス、それらを冷静に捉えていくというよりも、自分たちも一緒に体験しながら、その感情を捉えていきたいと思ったので、動ける機材というのも重視しました」。
今回の撮影現場では常に2カメ体制、多いときは4台のときもあった。「自分(Aキャメ)だけでなく、Bキャメも同じように動けるようにするため、チーフではなく、何本かメインで撮っている人に声をかけて、ダブル撮影カメラマン体制みたいなのを目指しました。また、最初はアナモレンズ(アナモルフィックレンズ)、昔のハリウッド映画がよく使っていたレンズを使い、70年代に近づいていくと、現代の新しいレンズをってクリアにするなど、時代の変化をレンズでも見せています」。
約4ヶ月という長い撮影期間で、特に「ゾクゾクした」と振り返るのは、デモやコザ暴動、民衆の力を目の当たりにするシーンだった。「好きなシーンはいくつもありますが、やっぱりコザ暴動のシーンで照明弾があがり、その明かりがグスクを照らすところ、すごく好きですね。そのシーンを含めて、照明の永田さんは照明弾に意味を持たせていますが、グスクの憤りや衝動が溢れ出る、その感情が一番よく表れたカットになりました」。
グスクを演じる妻夫木聡について、撮影現場で誰よりも近くで芝居を見てきた相馬は、「グスクそのものだった」と言う。「妻夫木さんとは、自分が撮影助手の時代に『ローレライ』でご一緒していて。その時から感じているのは、撮っている時も良いけれど、上がりはもっと良い、スクリーンに映し出されたものが格段に良いって、それはやっぱり凄い才能だと思うんです。しかも、彼は沖縄に縁があって、友人もたくさんいて、沖縄で生活している感じも芝居に活かされている。今現在の妻夫木聡がグスクとして生きている。沖縄の怒りや優しさをグスクとして表現していました」。
CLOSE ×
美術:花谷秀文
主な作品は『ハゲタカ』(09)、『大奥』(10)、『僕等がいた』前・後篇(12)、『アオハライド』(14)、『海難1890』(15)、『僕は明日、昨日のきみとデートする』(16)、『坂道のアポロン』(18)、『フォルトゥナの瞳』(19)、『きみの瞳が問いかけている』(20)、『ディア・ファミリー』(24)ほか。
+ INTERVIEW
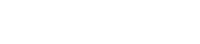
「全部が全部、毛細血管の全てに力を込めないとならないような、ロケであっても手を抜けないシーンばかりでした」と語るのは、『ハゲタカ』以来の大友監督作品への参加となる花谷秀文。「各現場でリアルを追求する、臨場感を大切にする、そこにかける比重がとても大きい監督だなというのは、前回も今回も変わらず感じました」。
辺野古のアップルタウンに作った特飲街のオープンセットは美術部の力作。ほかにも、ヤマコの家、嘉手納基地のフェンス、飛行機の墜落後、ゲート通り街並などの大掛かりなセットはもちろん、セットではないロケのなかで見せる細やかな仕事が、この映画をよりリアルに見せている。コンクリートやアスファルトの地面が土になっていたり、現代的な壁が石垣になっていたりする。「懐かしい風景だなと思えるような場所であっても、カメラが向けられるアングルのなかの3〜5割は現代のものが混在するので、美術による手術(1950〜70年の再現)が必要になります」。『宝島』で描かれる時代を再現する、作品のためであることは言うまでもなく、美術の役割には「役者たちをその世界に引きずり込む、映画のなかに引き込むことが美術の仕事だと思っているので、役者をその気にさせるためにも、頑張らないとって思います」。実際、主演の妻夫木聡をはじめどの俳優も、特飲街のオープンセットを見て、タイムスリップしたかのようなリアルな世界観に引き込まれたと語る。
そして「再現しようとすることから始まる」と振り返る。「映画はエンターテイメントなので、脚本に寄せて都合よく変えていくことも当然ありますが、それでも最初に目標とするのは再現です。今回は、公文書館やコザの図書館で沖縄の史実を調べたり、実際にコザにあるAサインバーなどに行って当時を知る人の話を聞いたり、いろいろな方法で取材をして再現に向かってアプローチしていきました」。なかでも一番難しかったのは、アメリカ統治時代である1950年代から70年代の20年間を段階を踏んで再現することだった。「再現するためのリアルを追っていくと、無理な部分、不可能な部分も当然出てきます。それを脚本に沿うように少しずつ修正をして、さらにリアルさだけではなく分かりやすさも加えていく。美術を物語のなかのランドマークにしていく、記号化していく作業です」。役立ったのは、プライベートで沖縄の歴史について調べていたことだった。「元々、戦後史に興味があって、沖縄に行ったときに戦跡巡りをしたり、いろんなガマを回ったり、書籍も読んだりしていました。もの凄く詳しいわけではないけれど、興味のある分野だったので、今回のお話をいただいて原作を読んだとき、熱量があって面白いと思ったのと同時に、昔かじりついた部分を掘り起こされて、自分のなかに空いていたスペースに『宝島』がカチっとはまったというか。これは凄い物語だって、わくわくしましたね」。再現から始まりアレンジを経て、映画『宝島』としての沖縄をつくり出した。
CLOSE ×
照明:永田ひでのり
『わが母の記』(12)で、第36回日本アカデミー賞優秀照明賞を受賞。主な作品は『旅のおわり世界のはじまり』(19)、『子供はわかってあげない』(21)、『この子は邪悪』(22)、『Cloud クラウド』(24)など。大友監督作は『影裏』(20)、『レジェンド&バタフライ』(23)を担当。
+ INTERVIEW
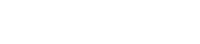
「二度、延期になっているので、スケジュールがあわなくなったスタッフもいましたが、大友監督の作品で、これまでやったことのないスタッフと仕事ができる、そういう機会を逃したくないという気持ちもありました」と語るのは、照明部を率いる永田ひでのり。『レジェンド&バタフライ』に続いての大友監督作品となる。照明部は、美術部や装飾部、撮影部との連携が特に必要な部署だ。事前準備をしながらも、美術や装飾が作り上げたセットによって調整も必要になる。「自分たちがいろいろと準備していたことが、覆されることもあります。ただ、撮影の相馬さんとは今回が初めてでしたがツーカーなところがあって。同じところで反応したり、同じ意見を持っていたり、だから大体うまくいきましたね。たとえ違うと思うことが出てきたとしても、準備したものが削られたと思うのではなく、だったらどうするかを考えます」。
撮影現場でスタッフ&キャスト全員が驚かされたロケがあった。オンをはじめ戦果アギヤーがフェンスを乗り越えて嘉手納基地に入っていくシーンだ。照明部はフェンスのずっと奥に50機近いライトを立て、ライトだけで基地の存在を描いてみせた。「何もない場所にまるで本物のフェンスが作られていて、それを見たとき、照明部は何ができるだろうと考えました。沖縄での撮影中に、関係者の計らいで嘉手納基地を見学する機会があり、その時に見た風景を、照明で再現できないかと。スケジュールも準備期間もなかったけれど、照明部の頑張りを見せたい、そんなふうに駆り立てられたというか、意地になったとうか、踏ん張りましたね」。
永田がこの『宝島』の撮影で大切にしていたのは、沖縄の人の気持ちだった。「撮影という仕事以前に沖縄の人はどんな気持ちで生きているのか、あの時代を生きていたのか──。自分が沖縄の人になったつもりでいようと思い、撮影中も何度もコザ十字路に行って、夜中も雨の日も、あの場所に立つことで何かを感じ取ろうとしていましたね」。
台本から何を読み取り、それをどう表現していくのかが、各部署の挑戦となる。照明部としてのこの作品における挑戦は、照明弾だった。「台本に書かれていたのは、浜辺で勝利の宴を開いているシーンで、“米軍から奪った照明弾を次々と打ち上げる”というト書き。そこだけでしたが、自分としては、オンちゃん(沖縄の人)の魂だと認識して、照明部でできる演出を大友監督に提案しました」。映画のなかでは、浜辺の照明弾を含めて3個所で照明弾が上がるシーンがある。「オンちゃんは沖縄のシンボル的な人だと解釈していたので、少年みたいなカラー、光を放っている感じを意識しています。あと、ヤマコは一番純粋な色を持っているキャラクターだと思ったので、ヤマコの家は澄み渡った綺麗な雰囲気が出るよう、寒色のフィルターを使っています」。
CLOSE ×
録音:湯脇房雄
主な作品は『貞子vs伽椰子』(16)、『オズランド 笑顔の魔法おしえます。』(18)、『劇場版TOKYO MER 走る緊急救命室』(23)など。大友啓史監督作品は『ハゲタカ』(09)、『億男』(18)、『るろうに剣心最終章 The Final/The Beginning』(21)、『レジェンド&バタフライ』(23)など多数参加。
+ INTERVIEW
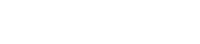
一見これは大変だろうな、と思うような環境(現場)であっても、そのなかでどう楽しむことができるのか、どう腕をふるわすのか、職人の腕の見せどころでもある。数多くの日本映画で活躍する湯脇房雄は、どんなに大変そうな撮影も「考えることが楽しかった」と『宝島』の現場を振り返る。
「僕にとって録音という仕事は、映画(作品)のリアルを追求することですが、そもそも映画(その作品)のリアルとはなんぞや?というところから始まります。録音には、同録(同時録音)もあるし、アフレコ(アフター・レコーディング)もあるし、いろいろな選択肢がある。その中で、アフレコよりも同録とオンリー(現場で特定の音だけを録ること)を選択するパーセンテージが高い。それが僕の基本です。アフレコは、できるだけしたくないんですよね。映画というのは、現実ではない嘘の画(世界)ではあるけれど、撮影という中においてはリアルです。だから映画のリアルを追求すると、同録という選択になるわけです」。
もちろん、役者の演技においても撮影現場と後日スタジオで再録音するのとではテンションが違ってくる。そのためにも、雑音(環境音、ジェネ音、風音など)をどう対処するのかも録音技師の腕にかかっている。「雑音があって、その音を消せないのであれば、どう対処するかを考えなくてはならない。何かの音を入れてごまかすか、その音が気にならないように別の音として作るか、いろんな方法がありますが、この場合はどうしようかと考えることが楽しいんです」。ちなみに、沖縄の空は数分おきに飛行機が通り過ぎる。撮影現場としては過酷な環境だった。
監督の演出によって録音の方法も異なる。大友監督と15年の付き合いになる湯脇は、大友監督の撮り方を知り尽くしているスタッフのひとりだ。「大友さんの場合は、引きがあっての寄り、その積み重ねなので、ワイヤレスマイクが主体です。どんなワイヤレスマイクを使って、どう録っていくのか、どう工夫するのか、いかに馴染むようにするのかを、考えていくのが僕らの仕事。分かりやすい例を挙げると、嘉手納基地からグスクが戻ってきて、フェンスを乗り越えて、ヤマコが「オンちゃんは?」と言って、その後、グスクとヤマコが走っていく一連のシーンがありますよね。あれも全部シンクロで録っています」。後日、アクションシーンの息づかいなどはアフレコで録っているが、基本は同録とオンリーだった。
そして、録音は録音なりの音の演出をすると言う。それはどういうことか?「専門用語が続くセリフのときは、(音のレベルを)普通に出していればいいけれど、ちょっと大事なシーンになったら、これは聞きなさいよってレベルを上げるし、逆にここはちょっと抑えて散らそうかなっていうときもある。その強弱を、僕の方で多少はつけています。演出側が音の演出を気に入るかどうかは分からないけれど。今回の『宝島』は、どっしりとした映画だから、そのどっしりとした形の中でどうするか、でしたね。大友監督とはそういう細かい打ち合わせは全然したことないですけどね(笑)」。
CLOSE ×
編集:早野 亮
『64‐ロクヨン‐前編』(16)で第40回、『護られなかった者たちへ』(21)で第45回日本アカデミー賞優秀編集賞をそれぞれ受賞。主な作品は『ラーゲリより愛を込めて』(22)、『九十歳。何がめでたい』(24)ほか。大友監督作は『3月のライオン 前編/後編』(17)、『億男』(18)、『影裏』(20)を担当。
+ INTERVIEW
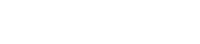
編集の早野亮は、カメラに収められた“うねり”をそのまま繋いでいくことを大事にした。「どの作品を編集するにしても、作品によって大きな違いはそれほどないですが、大友作品の場合は、素材が多い、カットが多い、そして尺が長い。それを比較的自由に、僕のほうで判断して繋いでくというのが、実は一番の特徴なのかなと思います。どのシーンも大切に撮ったものなので、良さを失わないように、物語のなかで何が重要なのかを自分のなかで構築しながら編集していきます。今回のように沖縄の20年間という長い時代を描く場合、物語を分かりやすくしがちですが、分かりやすくし過ぎると逆に面白くなくなってしまうので、じっくりすべてを見せることを心掛けました」。
3時間11分の物語。冒頭で、この作品の世界感にいかに入り込めるかも重要なポイントだ。戦果アギヤーたちが米軍から逃げるオープニングのカーチェイスシーンは、一番時間をかけたと語る。「この映画をどう観るのか、冒頭がその方向性にもなると思うので、最初にこれを見せたら3時間途切れることなく見せることができるのではないか、試行錯誤しながらでした。『宝島』という作品がもともと持っているテーマは大きくて重い。最終的にそれを受けとめてもらうために、入口(冒頭)は、その重さを感じさせないように、懐かしさと取っ付きやすさを意識しました」。
物語としてのヤマ場があり、主人公のグスクをはじめ、ヤマコ、レイ、オン、それぞれのヤマ場もあり、クライマックス的シーンがいくつもある。見どころだらけであることもこの映画の魅力のひとつだ。なかでも、約20分という長い尺で描かれるコザ暴動のシーンは、想像を優に越える熱量を放っている。「コザ暴動のシーンは、カット数も多くて、民衆役のエキストラの数も多くて、しかもみんながみんな素晴らしい芝居でした。カッコよく繋ぐとか壮大に繋ぐとか、そういったテクニカル的なことよりも、芝居のエネルギーを失うことなく丁寧にしっかり繋いでいく、それを第一に考えました」。まるでグスクと一緒にその場にいるかのような、没入感あるシーンになっている。
大友監督の意向を聞きつつ、編集の立場として、このセリフは寄りで言わせてみてはどうかなど選択肢は無限にある。「そういう意味では、ヤマコの家にレイが訪ねてくるシーンは、長回しで撮っているので、ワンカットにもできるしカットを割ることもできる、一番大変だったかもしれません。レイの気持ちに寄りすぎてしまうとヤマコの方が……となるので、そのさじ加減も含めて自分のプランを提示していくという感じですね」。
時間をかけたシーンや苦労したシーンがあるなかで、好きなシーンは何処なのだろうか。「やっぱり後半のグスクがすごく好きですね。ずっと溜め込んできたグスクの怒りがコザ暴動と混ざり合い、沖縄の人の感情を代弁するかのようなあの叫びへと繋がっていく。それまでのグスクは受け身というか、感情をそこまで表してこなかったけれど、爆発して、レイとの会話へと流れていく。あの一連の芝居は、何回見ても好きなぁだと思えるシーンですね」
CLOSE ×
VFXスーパーバイザー:小坂一順
主な作品は『キングダム』シリーズ(19/22)、『劇場版TOKYOMER 走る緊急救命室』『首』(23)、『ゴールデンカムイ』『碁盤斬り』(24)など。大友監督作は『るろうに剣心』シリーズ(12/14/21)、『3月のライオン 前編/後編』(17)、『影裏』(20)、『レジェンド&バタフライ』(23)を担当。
+ INTERVIEW
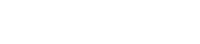
今や、どんなものもCGで描ける時代。架空の物語の世界を作ることもあれば、歴史の一部を再現することもあるが、どちらもそれぞれ難しさが伴う。『宝島』のVFXチームを率いるのは、小坂一順。大友監督作品では『レジェンド&バタフライ』に続いての参加、他作品では『キングダム』や『ゴールデンカムイ』シリーズなど(Spade&Co.として)150本を超える劇場用映画に携わってきた小坂であっても、『宝島』は挑戦だったと話す。
「1950〜70年代の沖縄に関しては、当時の建物や施設がほぼ残っていないこともあり、実はかなりの数のCGを使っています。たとえロケ撮影だとしても、抜けの建物はCGです」。VFXの作業を行ったカット数は、最終的に615に及び、約50人のスタッフが稼動した。「たとえば、戦国時代や明治時代の世界観を作る場合は、全国各地に城や寺が残っていますが、戦後の街並みの風景は沖縄も含めほぼ残っていないので限定した時代を再現するのは難しい。東南アジアなど似たような街で撮影する方法もありますが、それは現実的ではないので、街並という点ではオープンセットとスタジオのセットで撮影しています。『宝島』は言うまでも無く大作です。けれど大作だからといって予算も時間も限られていますから、美術と装飾と連携しながら、効率よくVFXを使うことを提案していく必要がありました」。どこまで美術と装飾が担い、どこからVFXが担うのか、境目がどこになるかで仕事の難易度は大きく変わる。
コザ暴動が起きたゲート通りは、日本最大のステージ、東宝スタジオの8スタにセットが組まれた。実際のゲート通りは、嘉手納基地の第2ゲートから胡屋十字路まで距離にして約500メートル。一方、スタジオの長さは41.8メートル。限られた空間で通りの奥行きをどう出すのか、群衆をどう描くのか、課題は山積みだった。「当初はオープンセットの予定で、ゲート通りの半径30〜50メートルくらいは美術が作り、その先がCGになるのではないか、最初はそう思っていました。ところがスタジオに変更になったことで、近距離の建物や人もCGで作らなければならなくなって──。エキストラは何百人も参加してもらっていますが、史実としてのコザ暴動は5000人の群衆です。しかも一人一人違う服を着て、髪形も違う、顔も映る、ごまかしがきかないんですよね」。救いだったのは、もともとオープンセットで準備を進めていたこともあり、美術部が木材など材料を無駄にしたくないと、店の形をしたブルーバックが作られたことだ。「通常は幕や平らな板を張りますが、今回は通りを挟むいくつかの店の外観の形をしたブルーバックを作ってもらい、なかなか特殊なセットになりました。ただ、そうすることで外観や看板に落ちる光や影がリアルになる。それは、メリットでしたね」。
コザ暴動の群衆のストレスやヘイト、爆発する感情は当然のことながらCGでは描けないが、その感情の強さと大きさと天秤になるような熱量のある空間を目指した。「炎や煙、爆発など画面の隙間がないようにCGで埋めました。自分たちも、グスクをはじめとする群衆のあの気持ちを表現したいと思って制作しています」。
CLOSE ×
装飾:渡辺大智
主な作品は『許されざる者』(13)、『世界から猫が消えたなら』(16)、『映画夜空はいつでも最高密度の空色だ』(17)、『ケイコ目を澄ませて』(22)ほか多数。大友監督作は『るろうに剣心』シリーズ(12/14/21)、『ミュージアム』(16)、『3月のライオン前編/後編』(17)、『億男』(18)、『影裏』(20)を担当。
+ INTERVIEW
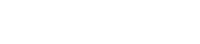
『るろうに剣心』シリーズをはじめ、数多くの大友監督作品の装飾を担ってきた渡辺大智。『宝島』映画化が決まる前に原作を手に取り、映画化される題材だと興味を抱いていた。その後、装飾として関わることが決まり、沖縄に関する書籍を集め研究するが、その数が半端ない。大きめの本棚ぜんぶを埋め尽くすほどの量。「この企画は二度の延期があったけれど、プラスに捉えればそれだけ調べる時間があったということ。3〜4年かけて調べることができて面白かった。沖縄という場所、島の感覚も肌で知りたくてプライベートで何度も訪れましたね」。地元の人と会い、話し、それを書籍で得た知識に加えていく。リサーチとしては無敵だ。「そうやって調べていくと、点と点が繋がっていく、その作業がすごく楽しい。たとえば、辺野古のアップルタウンに作ったオープンセットでは、看板やポスターなどは全部手書きです。当時はパソコンなんてない時代ですから、規定のフォントは使わずにデザインをおこすところから作業しています。Aサインの「A」の文字ひとつとっても、いびつなAだったりする。それも狙ってそうしています。看板屋さんに描いてもらったり、美大に通っている人たちに描いてもらったりしました」。看板の材料はもちろん古材だ。
装飾部のこだわりのセットと言えるのが、グスクの部屋だ。もともと台本にはなく追加されたシーンで、撮影最終日にスケジュールが組まれた。「主人公の部屋を何の準備もできない状態で撮影はスタートしましたが、毎日現場で妻夫木さんの芝居を見ながら、どんな部屋にするべきか考え準備を進めていきました」。そして、その方向性で間違いないと確信できたのは、撮影もラストスパートに差しかかった頃、ヤマコが教壇に立つ小学校に飛行機が墜落したシーンだった。「あのシーンのグスクの芝居を見て、準備してきたあの部屋でいけると方向性は固まりました。実は、それまで半信半疑で──。グスクは誰のためにオンを探しているのかが、つかめなかったというか。でも、泣き叫ぶヤマコを抱きかかえるグスクの芝居を見て、やっぱりグスクはヤマコのことが凄く好きで、オンちゃんを探す行動は、ヤマコのためなのだと繋げることができました」。床やベッドには資料が積まれ、壁には島の地図。そこに貼られた写真やメモの数から捜査の年月とグスクの執念が滲み出ている。また、二段ベッドが意味するのは人との距離感。刑事となったグスクの孤独さが際立つ仕組みになっている。「グスクは主人公だけれど、その心情は掴めるようで掴めない、そもそも刑事ですからね。ただでさえパーソナルな部分(ヤマコへの気持ちなど)を消している役柄なのに、なおかつ刑事としていくつもの覆面をつけている。だから前半の特飲街の撮影ではグスクの部屋に繋がるような心情を見つけることはできなかったけれど、そりゃそうだよな、こいつ刑事だしって気づいて。そうやって装飾としてグスクという役を提示していく作業が、とても面白かったんですよね」。まさに渾身のセットだ。
CLOSE ×
衣装デザイン:宮本まさ江
第36回日本アカデミー賞協会特別賞受賞。主な作品は『日本のいちばん長い日』(15)、『関ヶ原』(17)、『検察側の罪人』『日日是好日』(18)、『新聞記者』『キングダム』(19)、『燃えよ剣』(21)、『ヘルドッグス』(22)など。
+ INTERVIEW
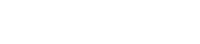
宮本まさ江は200本近い映画の衣装を手がける、日本映画を代表する衣装デザイナー。そんな宮本であっても『宝島』の規模感の衣装の演出は「大変だった」とふり返る。「沖縄を舞台にした映画は、過去にも『涙そうそう』や『チェケラッチョ』など何本か担当していますし、1950〜70年代の沖縄を記録したフィルムや写真があるので、そこから当時の人々がどんな服装だったのか雰囲気を掴むことはできます。けれど、そのまま再現というわけではなく、それをベースに、まずはグスク、ヤマコ、レイ、オンというメインキャラクターの衣装を考案し、『宝島』の世界観を作っていきました」。
俳優が身に着ける衣装によってそのキャラクターの見え方は左右される。各役の20年間の変化を見せることも重要だった。中心にいるグスクは、ベージュ、グレー、茶というようにベーシックな中間色が選ばれた。「他のキャラクターは年代と共に色や柄、デザインが変化しますが、その対比として、刑事になってからのグスクは(大地を感じさせるような色合いの)無地を選びました。1950年代のグスクは雪駄を履いているので、スーツのパンツラインは少し太めでツータックに。ただ、結婚以降は少し雰囲気を変えています」。ヤマコは、10代の少女が大人の女性に成長していく過程を衣装でも見せている。「たとえば、飛行機墜落事故のシーンのワンピースは優しさを感じさせる柄を選びました。デモのシーンは和製ジャンヌダルクをイメージ、実は私が若い時に着ていたジャケットを使っています」。レイは、和装の反物を100反ほど集め、その中から沖縄っぽくて柄がユニークでレイっぽいものを選んだ。「シャツ&ジャケットをベルボトムやニッカポッカと組み合わせています。ラストシーンはオンちゃんに寄せるかどうか迷いましたが、寄せずにレイらしさを見せる衣装にしました。レイの影響を受けているウタも、レイの衣装と同じラインでコーディネイトしています」。数ある衣装のなかでオンの衣装は、オン=英雄という記憶と共にみんなの印象に残る必要があり、かつオンらしさが滲み出る柄が求められた。「嘉手納基地ではぐれてしまった時に着ている衣装の生地は一点ものです。大友監督に見せたら「オンちゃんだ!」と柄に一目惚れでしたね」。
メインキャラクターの衣装の多くは宮本がデザインし、生地を選び一から作っている。もちろん生地にも柄にもこだわりがある。「グスクは無地のスーツですが、レイは着物の生地、沖縄らしい柄を取り入れました。沖縄の伝統工芸でもあるミンサー織りも使いたくて、オンちゃんの帯に使っています」。また、この映画の特徴のひとつとして、特飲街、民衆のデモ、コザ暴動などエキストラの出演シーンが多いことが挙げられる。「主人公たちを引き立たせるには、その背景にいる人たちがとても重要なので、エキストラの衣装を集めるなどして全部用意しています。大変ですが、大人数の撮影は楽しいし好きなんですよね」。多い日は300〜400人の衣装を用意した。
CLOSE ×
ヘアメイクディレクター:酒井啓介
主な作品は『妖怪大戦争 ガーディアンズ』(21)、『鋼の錬金術師 完結編 復讐者スカー/最後の錬成』(22)、『怪物の木こり』(23)、『ゴールデンカムイ』『八犬伝』(24)、『室町無頼』(25)など。大友監督作は『レジェンド&バタフライ』(23)を担当。
+ INTERVIEW
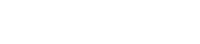
ヘアメイクディレクターの酒井啓介の準備も、実際に沖縄に行くところから始まった。「大友監督と話すなかで鍵となったのは、メインキャストしかり、エキストラの方も、沖縄出身ではない人をどうやったらメイクで沖縄の人に見せることができるかということでした」。沖縄に行って気づいたのは、住んでいる環境によって、肌や髪の質感に違いがあることだった。「まず日差しが強い。ナイチャーであれば1日で日焼けするくらいです。そういう土地で古くから暮らしているということは、基本的に肌が強いのかなと思いました。イメージとして、髭や眉毛、まつ毛が濃かったり、肌が浅黒かったりするのも環境によることが理解できたので、それを撮影でも意識して取り入れています」。グスクは刑事ということもあって日焼け感を出し、レイは刑務所に入っていた背景もあり一番白い、ヤマコもそれほど黒くはない、肌感もキャラクターの個性となっている。
1950〜70年という時代感を出すためには、粗さも必要だった。「アギヤー時代は、肌の質感を粗く作っているので、基本みんな汚れているし、黒い。腕や脚も同様に汚しのメイクをしています。グスクのメイクでいうと、アギヤー時代のメイクにかかる時間は40分くらい、刑事になってからは20〜25分ぐらいでした」。大変かつ大事だったのは、デモやコザ暴動など百人単位でエキストラが民衆役として登場するシーンだ。なかには400人という日もあった。「大友監督作品は『レジェンド&バタフライ』に続いて二度目。前回の経験があるので、大人数になることは予想していましたし、ひとりひとり作り込みが必要になることも分かっていたので、そういう日は10〜15人体制で臨みました」。
時代が移り変わるなかで、髪形をどうするのかが難しかったと言う。「1950〜70年代は、アメリカのファッションが入ってきて、パーマネントも入ってきた時代ですが、当時の沖縄は本土復帰前なので、映画でも描かれているように余裕がない時代なんですよね。そこをどう表現するかが難しかった。やりすぎると嘘になるし、リアル過ぎると地味になるというか。なので、嘘のない範囲でデザインをしていきました」。
また、アクションシーンでは、傷ができたり、血が出たりもする。その表現も酒井が担当する。「血糊で汚すなどは全部ヘアメイクがやっています。キャラクターによって、たとえば辺土名は鼻が曲がっている設定で特殊メイクをしているので、辺土名のときは百武さん(特殊造形・特殊メイク)にお願いしていました」。映画のなかでのヘアメイクは、美しく仕上げるのではなく、俳優をその作品の世界観に馴染ませる技術のひとつであり、スクリーンに映し出された俳優がリアルに見えるのは、ヘアメイクの力でもある。「一番神経を使ったのは、ラストシーンですね。頭から足先まで全身汚していますが、あの背景で、あの展開で、大友監督がラストの画に対して何を求めているのか、どういう画になっていくのか。現場で対応していく作業の方が多かったけれど、そういう現場で作り上げていくことが面白いんです」。
CLOSE ×
劇用車コーディネート:武藤貴紀
主な作品に、『シン・ゴジラ』(16)、『ドライブ・マイ・カー』(21)、『帰ってきたあぶない刑事』(24)、Netflix「新幹線大爆破」(25)など多数。
劇用車担当:金子拓也
主な作品に、劇用車として『ワイルド・スピード X3TOKYODRIFT』(06)、制作部として、『バトル・ロワイヤル』(00)、『LIMIT OF LOVE 海猿』(06)、テレビシリーズ「TOKYO VICE」(22)など。
+ INTERVIEW
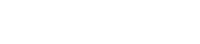
特定の年代を描くということは、あらゆるものを再現しなくてはならない。街並、身に纏うもの、当時売られていたもの……準備するものは多岐にわたる。車もそのひとつだ。劇用車を担当する武藤貴紀と金子拓也は、日本全国はもとよりアメリカなど世界から作品に見合う車を取り寄せた。マイケル・マン監督のドラマ「TOKYO VICE」など世界の監督と仕事をする彼らにとっても、『宝島』は「今までやったことのないレベル」だったという。
「リースと買い取り、借り物とあわせて、だいたい50台ほど用意しました。1950〜70年代という年代だけでも大変ですが、今回は左ハンドルのアメ車という条件も加わり、脚本を読んだときは、相当大変な作業になるぞと、二人で「やばい」を連発していましたね」(武藤)。
最初に選んだ車は、冒頭でオンをはじめ戦果アギヤーが米軍に追われるカーチェイスシーンで、グスクたちが乗っているトラックM 37だった。脚本のS#(シーンナンバー)1の1行目、ト書きには〈広大な基地内を猛スピードで走る軍用トラックと、それ追う米兵たちの軍用ジープ〉とある。「アメリカから購入したのでかなり値段は張りましたが、冒頭の一発目に戦果アギヤーが揃って登場するシーン、映画の顔(入口)になるシーンなので、『宝島』らしさを考えてM 37を選びました」(金子)。
『宝島』で描かれる当時の沖縄の街並にとけ込むことはもちろん、グスクやレイ、ウタなど、役に合う車をどう選ぶかも重要だった。美術部と装飾部と連携を取りながら、街と役にぴたりとはまる劇用車を用意した。「グスクが1950年代のシーンで乗っているのはシボレーです。おそらくアメリカのどこかの納屋にあったもので、錆びついたボディも色合いもぴったりじゃないかと思い、大友監督に見てもらうと「グスクの車だ!」と一目で気に入ってもらえました。僕らも絶対にこれだろうという自信はあったので、意見が合致して嬉しかったですね。ただ、このシボレーは不動車で、しかも当時のオリジナルなので今とボルテージ(電圧)が異なる。専属メカニックを沖縄に呼んで、撮影中ずっと対応してもらいました」(武藤)。修理をしながら撮影を行った。「レイはやっぱりオープンカー、少し派手めな感じが似合うのではないかと探していたら、香川でコンバーチブルのポンティアックチーフテンを所有している方を見つけて。お借りして沖縄に運びました。ウタの車は、ビートル(フォルクスワーゲン)のヴァリアントを用意しました」(武藤)。
特飲街やコザ暴動のシーンのなかには、車の衝突や炎上もある。それも本物の車を使って撮影を行っている。「動く車と動かない車を明確に分け、動かない車はヘッドライトを光らせて横転した後のシーンに配置し、各シーンのトーン合わせるために色を塗り替えている車もあります。今回のような規模はなかなかないので、胸が高鳴りましたね。ヴィンテージカーが集まってセットに配置されると、当時はこうだったのかなと雰囲気が伝わってくる。『宝島』に参加できて本当に楽しかったです」(金子)。
CLOSE ×
沖縄アドバイザー/沖縄ことば監修・指導:今 科子
主な作品は『おぎゃあ』(02)、『八月のかりゆし』(03)、『太平洋の奇跡 フォックスと呼ばれた男』『天国からのエール』(11)、『旅立ちの島唄〜十五の春〜』(13)、『島々清しゃ』(17)、『海辺の映画館 キネマの玉手箱』(20)、『島守の塔』(22)など。
沖縄ことば指導:与那嶺圭一
主な作品は俳優として『パッチギ!LOVE& Peace』(07)、「ガラス色の恋人」(09)、「琉神マブヤードラマシリーズ」(09〜15)、『天国からのエール』(11)、『天の茶助』(15)など。
+ INTERVIEW
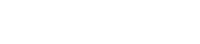
沖縄ことば指導としてクレジットされているのは、今科子、与那嶺圭一。今は、大友監督がNHK時代の演出作「ちゅらさん」も担当している縁もあり、『宝島』は脚本開発の段階からセリフ監修として参加している。どのぐらい方言を入れるのか、キャラクターによって方言の強弱をどうするのか──「言葉ひとつも妥協したくない。本物の言葉で撮りたい」と、何度もセリフの修正を行った。撮影現場で、今のサポートを担うのは、俳優としても活躍する与那嶺。方言指導として映画に参加するのは今回が初となる。「今さんのサポートをしながら、コザ暴動のシーンや戦果アギヤーがフェンスを越えていくシーンなど、役者としても3〜4シーン出演させてもらいました」。力強い戦力となった。
“ことば”は、時代によってどんどん変わっていく生き物のような側面もあり、沖縄ことばといっても市町村によって異なる。そのなかで今が何よりも大切にしたのは、1950〜70年代のコザの言葉であることだった。さらに、キャラクターによっても違いを出している。今と与那嶺が全セリフを録音し、役者はその音源を聴きながらセリフを覚える。それぞれの俳優の取り組み方を振り返る。グスク役の妻夫木聡については「完璧なウチナンチュだった」と絶賛する。「妻夫木さんは、コザに友達がいることもあり、沖縄のイントネーションはもともと完璧に近くて、コザの言葉も何パターンか教えると全部を把握していました。本当に沖縄の人でしたね」。ヤマコ役の広瀬すずは、教師であることから方言の割合を調整している。「当時は方言令もあり、教員はできるだけ標準語を使う時代でもありました。ヤマコに関しては、訛りを濃くせず、方言を入れても最後に“〇〇やさ”という感じに留めています」。レイ役の窪田正孝は、短期集中で練習に臨んだ。「撮影前に一度東京で練習をして、沖縄に入ってから稽古の日を作り、徹底的に練習してもらいました。窪田さんは、現場ではずっと標準語で喋っているので、最初は大丈夫かな?と心配していましたが、いざ段取り(テスト)に入ると完璧で。こちらを不安にさせながらも完璧にこなす人でした」。オン役の永山瑛太は努力家だった。「オンちゃんはコザの英雄なので、大友監督と相談しながら、他のキャラクターよりも方言を強調しています。瑛太さんは、ひと言であってもそのひと言をオンちゃんとして完璧にしようと努力する人でした。会話のなかで咄嗟に出てくる言葉も覚えておきたいとリクエストがあり、オンちゃんアドリブ集も作りましたね。また、今は「コザの思い、1950〜70年代の沖縄の人々の想いを伝えたい」と、コザ暴動やデモのシーンでは、エキストラのセリフにも力を注いだ。実際のコザ暴動の記録音源から群衆の言葉を一つ一つ書き起こし、当時を知る世代に話を聞き、それをエキストラのセリフに反映させている。「大友監督が、エキストラも役者のひとりだと言っているのを聞いて、沖縄出身じゃない方にもウチナンチュになってほしい、1人1人セリフを言って欲しいと思い、与那嶺さんと私でエキストラの方々に、短いセリフを覚えてもらいました。事前準備からクランクアップまで、とても大変でしたが、それ以上にとても楽しかった。本当にこの映画に関わることができて感謝しかないです」。
CLOSE ×
フードコーディネーター:嘉陽かずみ
琉球料理研究家の松本嘉代子氏の助手を務め、琉球料理を基礎から学ぶ。12年より観光客向けサービスとして市場ツアー&沖縄料理体験教室を実施するなど独自の世界を展開、県外への出張料理教室も多数実施。
+ INTERVIEW
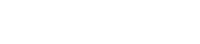
どの部署も脚本から何が必要であるかを読みとり準備をする。フードコーディネーターとして、この映画の“食のシーン”を任されたのは、琉球料理家で沖縄県観光大使(食部門)の嘉陽かずみ。ヤマコの就職祝い、法事や納骨といった大勢が集まるシーンは、伝統的な料理が並んだ。「沖縄で法事と言えばこの料理というように決まった料理があり、盛り付けに関しても形式があります。私自身、年齢を重ね、経験を積んでいるので、それを活かせると思い、喜んでお引き受けしました」
物語の舞台となるのは1950〜60年代。沖縄の街並は大きく変化をしているが、料理は時代と共に変化はあるのだろうか。「その頃と今と、ほとんど変わらないですね。最近は、業者が作ったものを用意することもありますが、昔はそれぞれの家で作っていました。メインになるのは重箱料理です。本土で重箱料理というと、お正月のおせちをイメージされると思いますが、沖縄の重箱料理は、ご先祖様にお供えするご馳走、それが重箱料理です。ですから、法事のときは必ず登場する料理ですね」。
撮影現場で、料理の準備をしていると、美味しい匂いにつられてキャストがふらりと立ち寄ることもあった。その美味しい中身とは──。「正式な重箱の大きさは約21センチ四方で、9つのマス目に沿って9品のお料理を盛り付けます。どこの地域でも大体決まっているのが真ん中のライン。角煮をラフテーと言いますが、地元では三枚肉の煮付けと言います。その三枚肉の煮付け、法事の時は白いかまぼこ、昆布、この3つは大体どこの地域でも決まったものがあり、その地域の産物が入ったりすると微妙に変わったりもしますね。ほかには、天ぷら、豆腐の揚げ物、お煮付け類など。今回は映画の撮影ということもあり、色味のバランスに気をつけながら、みんなが集まるシーンでは4段重ねの重箱料理を8つ作りました」。
大友監督は、その土地土地の風習を描くことも大切に『宝島』に臨んでいた。法事のシーンでは、時代考証、民俗考証のスタッフも交え、現場を作っていった。「重箱と一緒に仏前に飾るお菓子や果物の種類や配置にも決まりがあるので、時代考証や民俗考証の先生と一緒に準備をしました。器にも決まりがあります。わが家には大正生まれの姑がいて、当時の器を持っていたので、これ使えるかな……と現場に持っていたら、先生が「ばっちりです、これを使いましょう」ということに。その器をスクリーンで見るのも楽しみです(笑)」。食のシーンをとおして、語り継がれることの大切さが伝わってくる。
また、嬉しい再会もあったと話す。「ユタ役・照喜名(てるきな)を演じているきゃんひとみさん、昔に仕事をご一緒したことがあったので再会がすごく嬉しかったというのと、照喜名のセリフは、地元の人も話せないとても難しいユタの言葉(のセリフ)を方言で話しているんですね。そのお芝居を見て、鳥肌が立ちました」。食や風習を含め、沖縄で生きてきた人々が伝えるものが、カメラにはしっかりと収められている。
CLOSE ×
米軍所作指導:飯柴智亮
軍事コンサルタント。99年に米陸軍入隊。精鋭部隊の第82空挺師団に所属し、アフガニスタンで「不朽の自由作戦」に参加。08年に大尉に昇進。09年除隊。11年トロイ大学より国際政治学・国家安全保障分野の修士号を取得。様々な国・企業のコンサルを担い、現在はウクライナの最前線で従事。
+ INTERVIEW
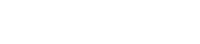
1950〜1970年代の沖縄を描くことには、アメリカを描くことも含まれる。グスクと協力して事件を解決する米軍の高官アーヴィンをはじめ、米兵も数多く登場する。彼らの米軍所作指導を担当したのは、映画『ランボー』を見てアメリカ軍人になった男、元アメリカ陸軍大尉で軍事コンサルタントの飯柴智亮だ。「お声がけいただいて原作を読みました。コザ暴動や小学校の飛行機墜落事故、戦果アギヤーについてなど、知らないことが描かれていて驚きました。米軍の人間として生きてきた自分の中で現在の沖縄は最重要地域、戦略上の重要な拠点であるという認識でしたが、『宝島』で描かれていることは、日本生まれの日本人として知らなければならないことでした」。それが映画に参加するきっかけにもなったと言う。
撮影現場では、具体的にどんな所作指導を行ったのか。「米軍入隊経験のない外国人俳優を、限りなく米軍の人間に似せることが最重要課題でしたので、今回は最初のオーディションの段階でドリル・アンド・セレモニーと言われる軍隊での基礎的な動き──気をつけ、休め、右向け右、回れ右、といった動きをやってもらい、向いている役者だけを厳選しています」。さらに、選ばれた俳優を本物の米軍の人間に近づけるため、所作はもちろん銃の構え方や軍人特有の言い回しなども指導した。「ここで苦労したのが1950~70年代の米兵、それも精鋭部隊ではなく空軍のSP(Security Police)レベルに特化させなければならなかったことです。当時には無かった動作や言語などを使わないよう、細心の注意を払いました」。映画の舞台は飯柴氏が産まれる前であるため、不明な部分は軍事技術体系の進化過程にスペキュレーション(推察)を織り交ぜて指導した。
撮影を通して、知らなかった事実を知る。そのなかで特に印象深く記憶に刻まれたのは、ヤマコが教壇をとる小学校に米軍の飛行機が墜落したシーンだった。「セットが大かがりだったことに驚きましたし、広瀬すずさんの演じるヤマコが泣き崩れるシーンがとても印象深くて──。自分は米ソの冷戦時代に育ち、米国の政策が最大公約数であると信じて米軍に入隊しました。完璧なシステムはない、絶対にないのですが、そういった中でアメリカが絶対正しいと信じて入隊したので、最大公約数であるがゆえに切り捨てられた数字があり、その切り捨てられた数字について、今までは致し方ないという考え方でした。しかし、この『宝島』のテーマがまさにそこを突いたものだったので、致し方ないで済ませてはならないことだと、深く考えさせられました。また、大友監督と話すなかで感じたのは、この映画を作らなかったら歴史の中に忘れられてしまう、だから映画を通して伝えたいんだという、とても熱い想いを持った監督だということですね」。
飯柴にとって映画に携わるのは今回が初めてとなるが、もともとシルベスター・スタローン主演の映画『ランボー』に憧れ、米軍に入隊するため19歳のときに渡米。自身の経験が映画作りに繋がるのはなんとも運命的だ。「『ランボー』を観て、今の自分の人生が始まったようなものなので、映画が人に与える影響はとても大きいと思います。そして、こうした『宝島』という映画に参加できたことも、すごく嬉しいです」。
CLOSE ×
スタントコーディネーター:吉田浩之
『孤狼の血』シリーズ(18/21)、『ラーゲリより愛を込めて』(22)、Netflix「極悪女王」(24)、『国宝』(25)など。ベストアクション監督優秀賞を2度受賞。大友監督作は『ミュージアム』『秘密 THE TOP SECRET』(16)、『3月のライオン 前編/後編』(17)、『億男』(18)、『レジェンド&バタフライ』(23)を担当。
ファイトコレオグラファー:後藤 健
主な作品はスタントコーディネーターとして『狐狼の血 LEVEL2』(21)、「インフォーマ」(23)、「ドンケツ」(25)、スタントとして『るろうに剣心』シリーズ、『HIGH&LOW』シリーズ、『キングダム』シリーズなど。
+ INTERVIEW
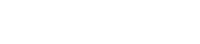
スタントを任されたのは、スタントコーディネーターの吉田浩之と、ファイトコレオグラファーの後藤健。彼らを筆頭に30〜40人のスタントマンが『宝島』のアクションシーンを支えている。まず、オンが率いる戦果アギヤーは米軍基地に忍び込むため3メートルの高さのフェンスを軽々と乗り越えるシーンがある。スタントチームは下準備と練習をしっかり行い、絶対に危険なことがないよう撮影に臨んだ。「想像以上に難しかったと思いますが、みなさん流石でした。驚いたのは、潜入するときに瑛太さんがフェンスの一番上からジャンプをしたことですね。高さもあるので、飛ばなくてもいいですよと話していたのですが、オンちゃんだったら飛ぶと思うのでと、役に入りきってジャンプ。流石だなと思いました」。
キャラクターごとにアクションの癖も用意している。「同じ戦い方にならないように、個性を出しています。オンちゃんとレイは兄弟なので、似ている部分があります。喧嘩慣れしていて、本能で戦っているようなイメージですね。一方、グスクは実直で熱い男ではあるけれど、実はそんなに戦うことが好きじゃなくて、フィジカルの強さというよりも気持ちで打ち勝つという感じですね。ただ、刑事になったグスクは武道も嗜んでいるはずなので、年齢によって違いを出しています。あと、俳優さんたちの芝居を見ながらですね。たとえば、グスクがホテルに拉致されてボコボコにやられるシーンがありますが、その時の妻夫木さんのお芝居を見て、感じたものを活かして(その場で)取り入れながら動きを作りました」。
大友監督は、芝居の延長線上にアクションがあることを常に大切にする、それは吉田と後藤が目指すアクションとも合致した。コザ暴動シーンを含め実はアクションシーンは多く、謎の男たちに米兵が襲撃される”アメリカー狩り”という事件の乱闘シーンも大変な撮影だったと語る。「“アメリカー狩り”をめぐり那覇派とコザ派が対立するシーンがあります。夜の狭い裏路地で、レイとタイラを含め約30人のアクションシーンでした。予定調和な動きにならないように、タイラがレイを助けて逃げる、階段からアクション部のスタントマンがゴロゴロ落ちるというドラマ(流れ)を作って撮影しています。そのシーンを大友監督がすごく喜んでくれて、「最高だった」っていう言葉をいただいたのは嬉しかったですね」。大友監督は琉球空手のアクションを取り入れようと考えていた。偶然にも後藤は琉球空手の三段所持者で、那覇派とコザ派の乱闘シーンには琉球空手も取り入れ、レイ役の窪田とタイラ役の尚玄も琉球空手を習い芝居に取り入れている。
また、クライマックスに用意されたグスクとレイの対峙について、「あのシーンは、妻夫木さんと窪田さんは100mぐらい全力で走ってから芝居が始まるので、負担はかなり大きかったはずです。それでも一連でやる意味のあるシーンで、これができれば見たことのない画になると思い、アクション部で何度も練習を重ね、絶対に危険のないよう準備をして臨みました」。走った後のアクション、そして5分にわたる熱量のある2人の会話は、言うまでもなく名シーンとして刻まれた。
CLOSE ×
監督補:田中 諭
主な作品は『ワンダーウォール 劇場版』(20)のほか、大友監督作品「ハゲタカ」(07)、「白洲次郎」(09)、「龍馬伝」(10)、『秘密 THE TOP SECRET』(16)、『るろうに剣心』シリーズ(12/14/21)など。演出として「おかえりモネ」(21)、「いいね!光源氏くん」シリーズ(20/21)、「どうする家康」(23)など。
+ INTERVIEW
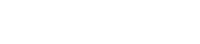
助監督としてキャリアを積み、大河ドラマ「どうする家康」の演出をはじめ、ドラマの監督としても活躍する田中諭。『るろうに剣心』シリーズ、ドラマ「白洲次郎」や「龍馬伝」では大友監督の右腕として撮影現場を動かし、今回の『宝島』では監督補として現場を支えた。もともと原作に興味を持ち、溢れ出る熱量に惹かれての参加となったが、今回の『宝島』も含めて、「日本が変わるタイミング(時代)を扱った作品、社会的な問題をエンターテイメントとして届ける作品、そういった大友作品に呼ばれるというのは嬉しいですし、縁を感じます」と語る。
どんなに規模の大きな作品であっても、大友監督のスタイルは変わらない。事前の打ち合わせは当然あるが「毎日がジャムセッションのようでもある」と言う。「大きな枠のなかで、各部署それぞれが自由にできる余白があって、こう考えてきたんですけど──と、現場ごとに即興演奏をするような感覚ですね。今回は監督補として、シーンごとに(芝居を含めて)イメージしているものを前のめりに提案する、それを意識していました」。
そのなかでも特に力を入れて向きあったのは、コザ暴動(騒動)のシーンとデモのシーンだった。「この映画は、沖縄史の一大クロニクル的な作品ですが、実はそのなかに、一人一人の正義や息づかい、未来が見えないなかで生きることに必死だった人それぞれが信じたものがある。主人公のグスクらが、正直に自分の正義を貫いているところがすごく響きました。コザ暴動は一夜の出来事ですが、沖縄で起きたその暴動をしっかり伝えたいし、描きたかった」。
ヤマコが参加するデモは沖縄で、クライマックスのコザ暴動は東宝の8スタで撮影されたが、どちらのシーンも数百人単位のエキストラ、多い時で500人近い日もあった。その一人一人をどう演出するのか、それを最前線で指揮していたのが田中だ。「大変でしたし、エキストラの方に時には厳しい演出もしたと思いますが、エキストラ担当の方から参加率が非常にいいと聞いて、嬉しかったですね」。民衆のなかで芝居をした妻夫木聡や広瀬すずは「エキストラさんの熱意に引っぱられた」と話しているように、「台本をめくりながら考えていること以上のことが、現場では起きる。コザ暴動のシーンは、最後の最後に全員が走り出してしまって、カット!の声も掻き消されるほどの熱量でした。原作や台本で感じていた人々の熱量が目の前で激しく湧き出て流れていく、あの熱量はちょっと感動しましたね。他のスタッフも「すげぇ!」ってなっていましたから」。
そして、俳優たちの、役を突き詰めていく姿にも驚かされたと語る。「妻夫木さんをはじめどの俳優も、こちらが十分だと思っても、まだ足りない、まだまだ足りないと役に向きあっていて、一体どこまでやるんだろうと。特に妻夫木さんは、沖縄の人たちが持っている柔らかさとしなやかさ、そして芯の強さと愛情をグスクとして体現していた。沖縄の人たちの想いをまるごと抱えているというか、見事にシンクロしていました」。
CLOSE ×
ラインプロデューサー:村松大輔
主な作品は『予告犯』(15)、『貞子vs伽椰子』(16)、『忍びの国』(17)、『3D彼女 リアルガール』(18)、『首』(23)など。大友啓史監督作品は『るろうに剣心』シリーズ(21)、『秘密 THE TOP SECRET』(16)、『レジェンド&バタフライ』(23)を担当。
+ INTERVIEW
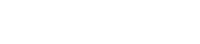
プロデューサーにも色々あり、現場に一番近い位置にいるのがラインプロデューサー。『宝島』では、村松大輔がその役割を担う。「簡単に言うと、現場の調整役、まとめ役ですね。日々、現場のみなさんから上がってきた問題や課題をどう処理していくかが主な業務で、そのなかには、撮影を止めないためにどうするのか、天候による撮影の決行・中止の判断もあります」。
『宝島』の撮影期間は、2月25日から6月9日の約4ヶ月間。前半は沖縄でのロケだったが、天候により撮影が中止となる日もあった。「沖縄=晴れというイメージがありましたが、実は天候が変わりやすかった。スケジュール担当の桜井(智弘)と、毎日ずっと天気予報のやり取りをしていました。あれほど天気予報のアプリを見続けた作品はこれまでなかったです」。多くの映画撮影では、雨の場合はスタジオや屋内の撮影に変更できるよう両天秤のスケジュールが組まれるが、『宝島』の場合は、ロケとオープンセットの割合が多く、スケジュールも苦戦した。「400人のエキストラさんに来てもらったデモのシーンがありますが、もの凄い土砂降りで……。晴れたとしても、地面が川のように水で溢れていたので、やむを得ずリスケに。再調整した日も曇空で小雨も降りましたが、結果的には、それもまた沖縄のリアルとして映し出されていて、地面が濡れている画のほうがデモのシーンには合っていたと思います」。
一方、撮影後半に組まれていた南紀白浜での撮影は天気が味方をした。旧南紀白浜空港の滑走路を嘉手納基地内に見立て、冒頭の戦果アギヤーと米軍のカーチェイス、グスクとレイの対峙からアーヴィンを交えたシーンまで、5日間にわたるナイター撮影。すべてフルオープンのロケで、予備日なし、撮影は延ばせないギリギリのスケジュールを乗り切り、クライマックスの感動シーンがカメラに収められた。
約4ヶ月間という長期撮影を無事に完走できた背景には、『宝島』特有のエネルギーがあったと言う。「これは結果論かもしれないですが、辺野古のアップルタウンに作った特飲街のオープンセットでの撮影が最初に組まれていたことも大きかったと思います。当時を知る人たちが特飲街のセットを見て「懐かしいね」と感動していて──そういう感想も含めて、こんなに凄いセットを作ってしまう作品に参加しているんだと、あのセットがスタッフ&キャストみんなのやる気をさらに上げてくれました。もし、それを考慮してオープンセットを最初にしたのであれば、スケジュールの桜井はかなりの策士ですね」。
撮影期間は106日、沖縄ロケは41日、ロケ地43個所、エキストラは延べ5000人、この数字からも作品の規模の大きさが伝わってくる。そして、撮影を支えた制作部は「縁の下の力持ち」だと村松は感謝を伝える。「毎日、撮影場所が変わるので、各部署の準備はもちろん大変ですが、現場のトイレカーをはじめとするインフラ整備、スタッフ&キャストの配車など、制作部も本当に大変だったと思います。そんな大変ななかでも、全員が常に『宝島』という作品の熱量に引っ張られている、そういう感覚のある現場でした」。
CLOSE ×
スクリプター:佐山優佳
主な作品は『14の夜』(16)、『ハルチカ』(17)、『キャラクター』(21)、『沈黙のパレード』(22)、『告白 コンフェッション』(24)など。大友監督作は『影裏』(20)、『るろうに剣心 最終章』(21)、『レジェンド&バタフライ』(23)、Netflix『10DANCE』(25)を担当。